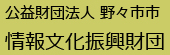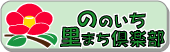ホーム » 随筆集 「林口川のほとりから」
「随筆集 「林口川のほとりから」」カテゴリーアーカイブ
中世史を逍遥
―伝統文化といわれるものの大半は、中世寺社に起源を持つ。能の創始者の観世は興福寺から出た。生け花は延暦寺末寺の池坊六角堂で始まった。茶道・作庭など寺社は日本文化の発信基地であった。(中略)今日も生きている寺社文化のナンバーワン、それは「日本語」である。都市・未来・上品・大衆・商人・観念・・、ごく普通に使われているこれら日常語は全部仏典から来ている。-
上の引用文は、08年に読んだ伊藤正敏著「寺社勢力の中世」に記された一節である。三矢が、歴史分野の書籍なかでも中世に焦点を合わせて読みだしたのは、この十年くらいのことだろうか。50歳半ばころより、郷土史に関わる知見を少しづつ蓄えるうちに、「承久の乱とは?」一向一揆での「百姓の持ちたるような国とは?」など、その時代背景をもっと深く知りたいという思いが募っていたようだ。
新書タイプや学術文庫に歴史ジャンルが豊富に揃い、また、近辺に大型書店が建って棚のスペースが広い分、直に手に取る機会が増えたことで、手軽に歴史分野の専門書が入手出来るようになったのも一因であろう。
「刀狩り」(藤木久志著)では、まず、*すでに早くかの秀吉の刀狩等をへて、いまや徳川時代の農民は全く武器を没収せられ・・*など堀田善衛(小説家)や羽仁五郎(歴史家)の一般的通念ともいえる認識を紹介。その直後に*天草一揆(1638)で没収されていた百姓の鉄砲324挺、刀・脇指1450腰、弓鑓少々・・*との、上記歴史通念とは正反対の史実を示す。
岩波新書のこの一冊は、それまで一般教養的にランダムに手にしていた彼の歴史書の読み方に、一つの軸を通してくれたようだ。同じ05年に、放送大学の教授でもある五味文彦の「中世文化の美と力」を手にしている。歴史と美術と両面からの興味で楽しめたこの冊子は、中央公論社から「日本の中世」として刊行された全12巻本の中の一冊だった。このシリーズは、他にも「分裂する王権と社会」(村井章介著)や「戦国乱世を生きる力」(神田千里著)を購入している。
05年以降の読書メモより、歴史ジャンルの書名を抜き出してみると89冊あり、この十年間の読書冊数比では14%弱、学術的な内容のものが多いので、時間的な比率では17~18%くらいか。その中で「中世」もしくは「戦国」という語が標題に入るものが三割強の33冊に及んでいる。また、これら89冊のうち読み応えありのマークが27冊、特に印象に残ったとアンダーラインを付したもの13冊と、他分野の本と比べ格段に確率が高いことが判かる。
最寄りの喫茶店で、一杯のカフェラテやカプチーノを飲みながら、これらの本のページをくる小一時間が、三矢にとって充足感にひたれるひとときでもあるのだ。
*戦国期に主力決戦や殲滅戦の事例は少なく、敵方の武将を味方につける「調略」の積み重ねによって勝利することが一般的であった。* 呉座勇一著「戦争の日本史」の一節だ。TVや映画での時代劇で、壮烈な戦闘場面を焼きつけられていると、武力で優位に立つものだと思い込みがちだが、いつの世でも多数を味方につけることこそ戦いを制する要諦と納得。
ベストセラーとなった井沢元彦著「逆説の日本史」も数冊手にしているが、中世混沌編中、一向一揆についての考察では、農民戦争などと分析する教科書の記述に対し、*それ迄支配者として君臨していた守護を排斥できたのは「国王・貴族といえども阿弥陀のもとでは一人の凡夫(平凡な人間)に過ぎない」という強烈な平等思想だ*と断定。*一向一揆という「民衆蜂起」は特筆大書され、前田利家という「封建領主」は無視されるというこの一点を見てもマルクス史学というものが、いかにくだらないか・・*と痛烈な批判を展開している。
中世後期の民衆が日常育んでいた生活・生産と直結する「意識」の問題を明らかにしたいと編まれた横井清著「中世民衆の生活文化」(上)では、*周知のように宮座(さらには講)を契機とし環境として成立する「寄合」は村落生活上の諸問題を自治的に協議、決定し、実現する場・・*と記す。これは、昭和40年代まで機能していた農村集落での「寄合」の淵源が、中世にまで遡れることを示してもいる。
漠然とした疑問や、なんとなく腑に落ちなかった事柄が、ランダムに手にした書籍の中で「これだったか・」という感じで、その手掛かりや答えを見い出した時、ミステリー小説での謎解きにも似た快感を覚え、こたえられぬ。
諸国大田文の具体例をあげながら、石井進「日本中世国家史の研究」では、*律令国家権力がある程度は分解しつつも、なお地方行政機関としての国衙の機能はかなり強固に残存していた。鎌倉幕府は公家政権から移譲された国衙機構支配権を大きなよりどころとして、成長・展開していった。*
現代の法治国家での、選挙で多数を制すると官僚機構はそれに従うというような慣例がない中世。鎌倉政権の全国的な支配実態を、ある程度明らかにする労作で益すること大だった。
散歩の途次に目にした草花や光景を記すがごとく、短い文節の引用を重ねてみたが、これらの書籍の内容はそう端的に要約できるものではないことは言わずもがな。このほか、速水融著「歴史人口学で見た日本」、末木文美士著「中世の神と仏」、網野善彦の名著「無縁・公界・楽」、河内祥輔著「頼朝がひらいた中世」など、独自の視点からの著作で、それぞれに楽しめた。
さらには、中橋大道著「中世加賀『希有事也』の光景」、栗原仲道編「廻国雑記 旅と歌」らを、郷土史的な関心から興味深く読んでいる。
(‘15・9・6作成)
長嘯子と守景

「あゝ、ここでも触れていたんだな」
三矢は、若年時の読書での理解力というか、読みの浅さに改めて思い至っている。その本は78年5月1刷、巻末に同年6月29日読了と記しているから、出版間もない。彼の30代半ばの頃だ。
-長嘯隠士のいはく、客は半日の閑を得れば、あるじは半日の閑をうしなふと。素堂、このことばを常にあはれぶ。予もまた、
うき我を さびしがらせよ かんこ鳥
とは、ある寺に居て言ひし句なり。―(注1)
引用文は尾形仂著「芭蕉の世界」第五回『笈の小文』の旅の一節である。蕉風の句を味わうにあたって、同氏はさらに数ページ後に次のような文を綴っている。
―木下長嘯子という人はどういう人か。本名を木下勝俊といって、秀吉の北の方寧子の甥に当る。もと若狭小浜藩主だったが、関ヶ原の合戦後、初め京都東山、のちに西山の山荘に隠棲し、隠者としては「冬の日」に出てきた、石川丈山の先輩格に当る人物。芭蕉たちからは、近世隠士のモデルと仰がれ、その家集「挙白集」は芭蕉たち蕉門の愛読(歌)書の一つになっていた。-(注2)
三矢はこの1月、Dキーン著「日本文学散歩」の分冊を読んでいて、数ページのコピーを残している。それにも木下長嘯子に言及する章がある。
-長嘯子が幽斎に師事して何を学んだのかははっきりしないが、中世の伝統に従って、和歌に奥義を習ったことは疑いない。おそらく幽斎は、近世の和歌の源である『万葉集』も長嘯子に手ほどきしたのだろう。しかし長嘯子の歌は、幽斎が吹き込んだ正統的な伝統に忠実であるよりも、むしろ清新で、因襲に束縛されない闊達な歌風のために知られることになった。-(注3)
この文節あたりが、蕉門に愛読された由縁を語っているのだろう。けれど、長嘯子が三矢の関心を引いたきっかけは、まったく別のところ。それは久隅守景描く「夕顔棚」だ。振り返ると、彼の学生時代に遡り、数学の研究成果によって文化勲章を受章した岡潔氏との出会いに始まる。
むろん、一介の学生と高名な数学者、直接の面識などあるはずもない。そのころ購読していた(昭和40年5月)、朝日新聞に掲載された同氏の随筆「春の日冬の日」。その文で受けた鮮烈な印象から、後に出版された「岡潔集」全五冊の購入(昭和44年初版)へと続き、次文の「夕顔棚」とのつながりだ。
―好きな画家は大観と久隅守景、外国ならゴッホ、ラプラードなどである。(略)
守景の実物は見ていないが、ある画家から新聞に出ていた写真版の「夕顔棚」を見せられ好きになった。この絵には半裸の夫婦よりも、それを見ている作者の気持ちが描かれている。いいかえれば、日常茶飯事にあらわれている心の動きを描いている。私自身いつも情緒だけを取り出して、それを見ようとしているのだから、こんな絵が好きになるのだともいえる(後略)-(注4)
残してあった資料やそれに記されたメモによれば、三矢が守景を最初に意識したのは’90年10月、石川県立美術館にある屏風「四季耕作図」で受けた感銘が原点。その直後に、岡潔集第二巻を再読しこの文節に出会うのだ。さらには’95年1月に開催された特別展“屏風絵の美”での「四季耕作図」との再会。その展観での感想文を送付したところ「石川県美術館だより」114号に全文紹介のハプニングも。
これらに混じり、守景に関する新聞記事(95・1 96・2 96・5)のスクラップなども挟まれ、加賀藩と守景の深い縁なども知見として加えている。ただ、この時期は、単なる庶民とは思えぬ人物?何か曰くがある・? 不思議なモチーフの絵と思いながら、絵の持つ魅力に気持ちが傾いていた。
その後も、金沢出身の藤岡作太郎著「近世絵画史」で、
―探幽門下で四天王の一人、加州候に仕ふること凡そ六年。画くところ豪放奇抜、法格に拘わらず。伝えいふ、守景その師を凌しを以て、破門せられぬと。-(注5)
など断片的な知識は増している。
「夕顔棚」の夫妻が、歴史上名のある人物の故事を作画上の動機としたとすれば、長嘯子の来歴を知った今、守景描くチョンマゲ姿はその人では・・と解釈しても、あながち、的はずれでもないだろう。
守景についてもう少しチェックしようと三矢は、本棚から「万有百科事典・美術」を取り出した。久隅守景の項には「夕顔棚納涼図」が載っており、
-紙本淡彩、二曲一隻、国宝。当時の風流隠士、木下長嘯子の「夕顔のさけるのきばの下すずみ 男はててれ(襦袢)めはふたの(腰巻)して」という和歌に取材した軽妙洒脱な絵―(注6)
との、まさにドンピシャの解説文。
長い年月の間、長嘯子や守景に関する断片的な情報を少しづづ蓄えるなか、最後に残った孔を埋めるかの切片を手にした三矢の胸中。それは、こま切れの断片が少しづつつながり、元の絵が徐々に浮かび上がってくるジグソーパズルの完成にも似た印象だ。
以下、D・キーン氏から再度引用する。
-1598年の秀吉の死、その二年後豊臣・徳川の戦端が開かれた。長嘯子の父家定は、姫路城に封ぜられており、徳川方についた。が、長嘯子の場合は、選択は明らかにずっとむずかしかった。彼は、豊臣秀頼と徳川家康の双方から、それぞれ、自軍のために伏見城を守れという命令を受けていた。石田三成の攻撃に対して城を守っていた軍勢の中には、徳川家名代の忠臣鳥居元忠があり(略)討ち死にした。彼も三成の軍勢に対して城を死守すべきか、それとも豊臣家の多年の恩顧に報いるべきか。日本の武士の伝統に従えば、これは切腹して然るべき状況である。ところが長嘯子は、城を脱出して京都に引きこもってしまった。-(注7)
徳川・豊臣の覇権争いに、あちらを立てればこちらが立たず・どの道を選んでも、身内や部下を見捨てることになる。そうした苦衷を味わう立場から逃げ出し「武士としてあるまじき・」との批判をあびた身であってこそ、長閑で穏やかな夕涼み・。その時間の貴重さというか、下世話ともいえる絵の含意が納得できる。
(‘15・9・6作成)
参考文献
注1・注2: 尾形仂著「芭蕉の世界」
注3・注7; ドナルド・キーン著「日本文学散歩」
注4 ; 岡潔集第二巻 -160-
注5 ; 藤岡作太郎著「近世絵画史」-27-
注6 ; 万有百科大事典・美術 -180-
書籍で拡がる絵画鑑賞 -10年間の読書メモよりー
絵画を主題にした書籍といっても、その視点は多様で読みだすとキリがない。‘05年以降の読書メモより、これに類するタイトルを抜き出してみると、その年により多寡はあるが通算で79冊になった。数量的な比率では10%くらいだが内容は概して軽いものが多いので、私の読書時間の中では7~8%くらいの位置だろう。
まず、画家やその作品への関心が、こうした書籍へ目が向く最初の動機と言える。「スペイン・ゴヤへの旅」(中丸明著)、「フェルメールの世界」(小林頼子著)、「ゴッホーこの世の旅人―」(A/Jルービン著)、「ポール・ゴ―ガン」(ヴァルター著)、「ロート・レック」(M・アーノルド著)、「レオナルド・ダ・ヴィンチ」(田中英道著)、「ミレーの生涯」(A・サンスイエ著)など欧州画家の伝記的著作が挙げられる。* 岩を荒地と思わぬ感情。自然を人間と対立するものではないと考える精神。それこそがレオナルドの自然描写をして東洋の山水画に近いと感じせしめる原因でもある。*これは、上記「レオナルド・ダ・ヴィンチ」の中の「岩窟の聖母」に触れた文節だが、作品そのものと対話しながら、なおかつ、北宗時代の郭煕と対比するなど、単なる伝記的な記述を超えた田中氏の著作は印象深かった。
日本の画家では、「画狂人北斎」(瀬木慎一著)、「岩佐又兵衛」(辻惟雄著)、「河鍋暁斉」(J・コンドル著)、「北斎万華鏡」(中村英樹著)、「高橋由一」(古田亮著)、「写楽」(中野三敏著)等々。江戸時代の画家に関心が向いているが、蔵書の中でも幾度も読み返している一冊「北斎万華鏡」は、K氏とマリオンの対話という形式で文章が綴られ、「富嶽三十六景 神奈川沖裏」を例に、* 描写された事物が何なのかよりも、むしろ描き手と外界とのかかわり方が、絵から読み取られるべきだ* とし、* 遠くかけ離れた両者を一つにするところに風景と〈関係〉する見る主体の強靭な構造がある* と中村氏は北斎を評する。
歴史的な視点では、「現代絵画入門」(山梨俊夫著)、「絵画の二十世紀」(前田英樹著)、「フランス絵画の『近代』」(鈴木杜幾子著)、「近代美術の巨匠たち」(高階秀彌著)、「世紀末画廊」(渋澤龍彦著)、「日本近代美術の魅力」(金原宏行著)、「日本洋画の曙光」(平福百穂著)、「中世の秋の画家たち」(堀越孝一著)、「西洋近代絵画の見方・学び方」(木村三郎著)、「中国絵画入門」(宇佐美文雄著)などがある。この手の著作では、作品や作家登場の時代的な背景やその位置づけなどが分かり「なるほど・」と納得がいく。その反面、次々と作家名が入れ替わり、通覧的になるゆえ、概して記憶に残りにくいきらいがある。
「絵画の二十世紀」は、* 写真の登場によって、二十世紀の画家たちは、物を見た目そっくりに描くことを超えて、絵画の新たな役割・手法を模索する* その代表例としてマチス・ピカソ・ルオー・ジャコメッティを取り上げ、個々の作品にそって前田氏は分析を試みている。歴史的といえば、「ビゴー日本素描集」、「絵で見る幕末日本」(アンベール著)、「ワーグマン日本素描集」(清水勲編)などは、江戸から明治への激動期に、当時日本に居住していた外国人が目にした絵画による記録であり、その客観性と合わせ興味をそそられた。
作品の特定ジャンル別の著作では、「江戸の花鳥画」(今橋理子著)、「日本の自画像」(桑原住雄著)、「描かれた女たち」(塩川京子著)、「江戸俳画紀行」(磯部勝著)、「漫画言論」(四方田犬彦著)、「マンガは哲学する」(永井均著)、「浮世絵カラー版」(大久保純一著)、「名画とファッション」(深井晃子著)などがある。とくに、「江戸の花鳥画」は、歌川広重や酒井抱一の図版を多数例示しながら、* 抱一や広重の活躍した19世紀の江戸においてもまた、「博物学」という「知」の体系が、実は驚くほど成熟し、すすんでいた* との新しい視点を提示し、印象深かった。
絵画の愉しみ方というか、観賞法的な著作では、「絵画の揺り藍」(A・ワルノー著)、「芸術力の磨き方」(林望著)、「日本美術の心とかたち」(加藤周一著)、「日本美術 傑作の見方・感じ方」(田中英道著)、「謎とき広重『江戸百』」(原信田実著)、「絵画について」(デイドロ著)、「フェルメール全点踏破の旅」(朽木ゆり子著)、「謎とき洛中洛外図」(黒田日出男著)、「絵画の向こう側」(中村隆夫著)など、それぞれに特異な視点からの画評を愉しみつつ、鑑賞の仕方の幅を広げている。
画家自身もしくはその親族の手になる「ノアノア」(ポール・ゴーギャン著)、「泉に聴く」(東山魁夷著)、「岸田劉生随筆集」(酒井忠康編)、「女」(山本容子画文)、「麗子と麗子像」(岸田夏子著)、「似顔絵物語」(和田誠著)、「顔ブレ」(大岡立似顔絵集)、「挿絵画家・中一弥」、「絵のある人生」(安野光雅著)、「ちひろ美術館ものがたり」(松本由理子著)など、自伝もしくはエッセイとして、舞台裏をのぞくような気分が味わえる。中でも、文明の汚濁から逃れようとタヒチに渡ったゴーギャン。そこで、* かって、私はわざわざ事をやっかいにしていた・・ところが、見たそのままを描くことはじつに簡単なことであった。カンバスのうえにたいした計算もなしに、ひとつの赤を、ひとつの青を置くことは!* と開眼。現地の若い娘テウラと生活を共にする中から、生命の根源に迫るかの絵を産みだした。
書店や図書館の陳列棚から、その時々の関心で選び出した著作物。そんな脈絡のない行為の集積とは言え、このように抜粋整理してみると、見えて来るものがある。すなわち、7~8時間費やして、一冊の本を私が読み続けるのは、上にいくつか引用したような文節に出会える愉しさに支えられているからなのだろう。
(‘14・12・26作)
写楽の手
ガラス製のペーパーウェイトやボールペンが机上に散在している中、それらを見るともなく目にしながら、三矢は、今抜き書きしたばかりの一文を反芻している。
-確かにヘンテコなバランスの悪い奇妙な手ではある。しかし、何より重要なことは観るものに訴える力である。-
これはカラー版で付された口絵「五代目大谷鬼次の奴江戸兵衛」に対する著者の評の一節だ。彼が読み終えた本は、秋田巌著「写楽の深層」。
著者秋田氏は、
-精神科医、ユング派分析家として訓練を積んできている。-
-百四十数点の写楽画コピーをパラパラめくっているうちに一瞬にして(といっても数分くらい?)写楽の心的プロセスが読み取れた。-
と言い、写楽は「自己絵画療法」として作品を描いたと、数多い写楽論とは一味違う視点での論を綴った興味深い一冊だった。
―「奴袖助」の拳は「よし、やるぞ」であると同時に、「どうだ、俺はやったぞ」である。それら二つの強い気持を同時に見てとれる。-
-「江戸兵衛」を「江戸兵衛」たらしめているのは、他ならぬこの「手」である。-
等々、手の表情というか、手の動きに現れた心理描写に関わる幾つかの文節に接するうちに、三矢は清岡卓行の「手の変幻」という著作を思い起こしていた。愛読というほどではないが、書架の背文字を眺めているうちについ手にして再読するというかたちで、一再ならず読み返し、その都度感銘をあらたにしている本だ。
例えば、東京オリンピック女子バレーチームが対ソ連戦に勝って優勝が決まった瞬間の映像シーン。
-ぼくはここで、ただ、彼女たちの手が驚くほど生き生きと感情の高まりを表現していることを、繰返し指摘したいだけである。-
あるいは、映画「かくも長き不在」の映像から
-彼女はちょうど店の日除けのハンドルを廻している。しかし、浮浪者が眼の前を通ったとき、彼女は彼の顔をまじまじと見て驚愕する。ハンドルを廻していた両手は、ぴたりと止まったまま動かない。(略)この時の凍りついたような両手(スチール)、それは極めて印象的・・(略)-
などの文が、彼の心に喰い込むように強くせまるものだったからだ。
秋田・清岡の両者に共通するのは、手や指先の僅かな形姿の変化のなかに、その人の心の微妙な動きを読み解くという点であろう。秋田氏に戻れば、手の指が六本もありそうな描き方について、
‐江戸兵衛の「手」はもはや“歪み”のレベルを超えている。絶対絶妙のアンバランスであり、破形の“歪み”である。-
と喝破するくだりなど、三矢の心にもストンと落ち込み、絵画評としても一流だと感じた。
M書店の奥まった書架でこの著作を手にしたとき、彼は、これまでに数冊の「写楽」本を読んでいることが記憶の片隅にあった。本棚の一隅に隠れていた読書メモ帳が、三度目かの探索でようやく見つかったので、念のためとしらべてみると、‘97~’01年の間に「私が写楽だ -十返舎一九の推理―」(鷹羽一九哉著)、「写楽」(皆川博子著)、「真説・写楽は四人いた!」(村中陽一著)、「写楽・仮名の悲劇」(梅原猛著)の四冊があった。
秋田氏が参考文献に挙げていた中野三敏著「写楽」には、昭和64(´89)年までに出版された写楽別人説の一覧表が記載されていて、それと比較すると、梅原氏の一件だけが一致し、残りは昭和64年以降の小説とあって対象外。中野氏の一覧表にリストアップされているのが41件。三矢が手にし、ここに作者名をあげたものだけでも5冊。いかに、写楽という画家がミステリアスな存在で、多くの人たちから深い関心を寄せられているかの証左とも言えよう。
(´14・10・8)
重兼芳子との再会
― 幼少期の股関節脱臼が原因で幾度目かの外科手術を受けたばかりの病室へ、一通の速達が届いた。文面は《「まくた」創刊号に書かれた貴殿の「水位」という作品を、当社発行の「文學界」に転載したいので御諒承ください》というものだった。-
ここから、カルチャーセンター出身の芥川賞作家誕生までの顛末が綴られる。
夏の日永どき、朝夕の無聊を凌ぐため軽いエッセイ集でもと、三矢が図書館の書架から抜き出した一冊の本重兼芳子著「女の一生曇りのち晴れ」である。
本の末尾の筆者紹介欄には、1979年「やまあいの煙」で第81回芥川賞受賞と記されている。
彼にとって30歳代後半からの10年間余は、コンピュ―タを利用して事務作業を効率化するという、きわめて多忙な時期を過ごしていたため、小説など求めて読むことは殆どなかった。ただ、三矢の20歳代に継続購読していた月刊誌が「文芸春秋」だったので、その延長線上、話題を呼んだ芥川賞受賞作だけは、同誌を求めたり図書館で借りだすなどして読んでいた。その中でも、重兼芳子の「やまあいの煙」は印象に残った作だったようで、多数のエッセイ本の中から「作家名に覚えがある、確か芥川賞?」と、一瞬の判断で借り出したものだ。
- 強固な地盤に立っていると思い込んでいた私の足許が、ずるずるとなし崩しに崩れてゆく。その頼りない不安がなぜくるのか、自分の存在がどこにあるのか。私は悩み続けた。そうして最後の作品として「水位」を書いたのだ。姑や家族に見つからぬように皆が寝静まった夜中に、こっそりと起きて机に向かった。-
-「文學界」に転載されるということは、同人誌にのった千篇近い小説の中から選ばれたことになる。-
-地下室でのリハビリテーションは、私にとって地獄となった。そんな中、もう一篇だけ、「水位」の次にもう一篇だけ、小説を書きたい。と病室の毛布の中に電気スタンドを入れ原稿用紙を広げて、二度目の芥川賞候補になった「髪」という作品は、少しずつその形を整えていった。-
これ以上引用すると、単なる要約となるので止めるが、こうした作家の心の懊悩というか、人生への立ち向かい方が三度目の候補作「やまあいの煙」に反映されて、彼の心の琴線に触れるものがあったのだろう。
借り出した本の文章は、引用文からも分かるように行きつ戻りつで、ある意味では粘っこく、途中で投げ出したくなったこともある。しかし、読みついでみると「金と暇のある主婦作家」というマスコミが流布させたイメージとはかけ離れた読後感となった。
この本のカバー裏に貼られた返却期限票は、二枚重ねになっており、平成10年までで75回あまり。本は昭和59年12月初版とあるから、読者の共感を呼ぶかなりの人気本だったと推察させる。
三矢とは15歳年上の作者は、敗戦を18歳の青春期に迎えている。多感な時期に時代の大転換を経験した重兼氏の人間観察は、ぐさりと読む者の肺腑をえぐる。
最後にもうひとつ著者の述懐を引用しよう。
- どんな思春期を過したか、どんな家庭生活を送ったかというインタビューを受けるうちに(略)今在る私という存在は、どんな変遷を経て私という人間が構成されたのか、それを問いかけなければ、なにもはじまらないのではないかと思うようになった。ー
(‘14・7・23)