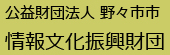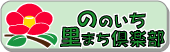ガラス製のペーパーウェイトやボールペンが机上に散在している中、それらを見るともなく目にしながら、三矢は、今抜き書きしたばかりの一文を反芻している。
-確かにヘンテコなバランスの悪い奇妙な手ではある。しかし、何より重要なことは観るものに訴える力である。-
これはカラー版で付された口絵「五代目大谷鬼次の奴江戸兵衛」に対する著者の評の一節だ。彼が読み終えた本は、秋田巌著「写楽の深層」。
著者秋田氏は、
-精神科医、ユング派分析家として訓練を積んできている。-
-百四十数点の写楽画コピーをパラパラめくっているうちに一瞬にして(といっても数分くらい?)写楽の心的プロセスが読み取れた。-
と言い、写楽は「自己絵画療法」として作品を描いたと、数多い写楽論とは一味違う視点での論を綴った興味深い一冊だった。
―「奴袖助」の拳は「よし、やるぞ」であると同時に、「どうだ、俺はやったぞ」である。それら二つの強い気持を同時に見てとれる。-
-「江戸兵衛」を「江戸兵衛」たらしめているのは、他ならぬこの「手」である。-
等々、手の表情というか、手の動きに現れた心理描写に関わる幾つかの文節に接するうちに、三矢は清岡卓行の「手の変幻」という著作を思い起こしていた。愛読というほどではないが、書架の背文字を眺めているうちについ手にして再読するというかたちで、一再ならず読み返し、その都度感銘をあらたにしている本だ。
例えば、東京オリンピック女子バレーチームが対ソ連戦に勝って優勝が決まった瞬間の映像シーン。
-ぼくはここで、ただ、彼女たちの手が驚くほど生き生きと感情の高まりを表現していることを、繰返し指摘したいだけである。-
あるいは、映画「かくも長き不在」の映像から
-彼女はちょうど店の日除けのハンドルを廻している。しかし、浮浪者が眼の前を通ったとき、彼女は彼の顔をまじまじと見て驚愕する。ハンドルを廻していた両手は、ぴたりと止まったまま動かない。(略)この時の凍りついたような両手(スチール)、それは極めて印象的・・(略)-
などの文が、彼の心に喰い込むように強くせまるものだったからだ。
秋田・清岡の両者に共通するのは、手や指先の僅かな形姿の変化のなかに、その人の心の微妙な動きを読み解くという点であろう。秋田氏に戻れば、手の指が六本もありそうな描き方について、
‐江戸兵衛の「手」はもはや“歪み”のレベルを超えている。絶対絶妙のアンバランスであり、破形の“歪み”である。-
と喝破するくだりなど、三矢の心にもストンと落ち込み、絵画評としても一流だと感じた。
M書店の奥まった書架でこの著作を手にしたとき、彼は、これまでに数冊の「写楽」本を読んでいることが記憶の片隅にあった。本棚の一隅に隠れていた読書メモ帳が、三度目かの探索でようやく見つかったので、念のためとしらべてみると、‘97~’01年の間に「私が写楽だ -十返舎一九の推理―」(鷹羽一九哉著)、「写楽」(皆川博子著)、「真説・写楽は四人いた!」(村中陽一著)、「写楽・仮名の悲劇」(梅原猛著)の四冊があった。
秋田氏が参考文献に挙げていた中野三敏著「写楽」には、昭和64(´89)年までに出版された写楽別人説の一覧表が記載されていて、それと比較すると、梅原氏の一件だけが一致し、残りは昭和64年以降の小説とあって対象外。中野氏の一覧表にリストアップされているのが41件。三矢が手にし、ここに作者名をあげたものだけでも5冊。いかに、写楽という画家がミステリアスな存在で、多くの人たちから深い関心を寄せられているかの証左とも言えよう。
(´14・10・8)