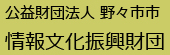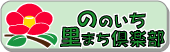最近この店で、お気に入りになった抹茶ラテ。残り少なくなったその濃い緑色と雪のような白いラテの混ざり具合を、ゆっくり味わいながら、三矢は窓外に視線を転じた。総ガラス貼りの壁面を隔てて、道行く車や駐車場に出入りする人たちの様子が手に取るように見える。あわただしい師走の街かどだが、きれぎれの雲間より、淡い冬の陽差しが覗き、しばしのやすらぎを醸しだしている。
3月に「イギリスからの賜り物」を記してから、次はドイツになるだろうと簡単なメモを残して置きながら、書き出しはゲーテかニーチェか。デュラーやベートベンもいると迷っている間に、いつしか年の瀬を迎えてしまった。
この間、金沢市民劇場の例会の一つに、抗ナチズムに命を捧げた女子学生を主人公にした「白バラの祈り」という劇が上演され、ヒロイン『ゾフィー』が吐くセリフに「ドイツの誇り、それはゲーテやシラーだ。ベートベン・ワグナーもいる・・」云々があって、彼も「やっぱりね」と肯いている。
生き方や己の存在の根源を揺さぶるようなニーチェの数々の文節。アフォリズムの宝庫とも言える中から、一つだけ採り上げよう。
― 芸術衝動には、過剰・陶酔・激情にむかうディオニュソス的(酒神)なものと秩序・明晰・静観・夢想の方向に進むアポロン的(太陽神)の二種類がある ―
講談社刊の「人類の知的遺産54 ニーチェ」の巻末に、鉛筆で記入されているのは「’91・3・7読了」の文字。この年の1・2月、比較的ゆったりと読書時間がとれる頃のこと、一言一句を味わいながら読んでいたらしく、抜き書きもダントツだ。
ゲーテは、河出書房社刊「世界文学全集2 ゲーテ」が書棚に残っている。
読了日は1960年9月とあるから、50年以上も前で、彼にとっては、青春時代真っ只中での読書。その頃は、併載の「若いウェルテルの悩み」の方に感激していたようだ。’01年と’03年に「ファスト」を改めて読み直しているが、人生経験を重ねないとその味わいが解らない文章が多い。
― 金も医者も魔法もなしに、若返らせる方法。
すぐに畑に出かけて
耕したり、掘ったりし始めなさい
そして、身も心も
ごく限られた範囲に閉じこめておくのです。
まじりけのない食物でからだを養い、家畜といっしょに・・(略)-
というメフィストの言葉などに、カラーペンのマークが印されている。
春から秋にかけて、三矢は2haの水田の稲作に従事している。適度の労働と自然環境との交感に、日々充足を感じているが、ゲーテのこの文節などが、精神的なバックボーンとなっているようだ。
机の上に、本棚から抜き出したばかりの新潮世界文学37「ヘッセⅡ」がある。作者の写真を表紙に配した、800ページ余の分厚い文芸書だ。その中で半分近いページ数を占める「ガラス玉演戯」は’87・1月読了の書き込みがある。文芸書はほとんど読まなくなっていたこの時期に、再読であれ書棚から取り出しているのには、それだけの思い入れがあったのだろう。
高校生の夏休み読書感想文コンクールの推奨リストの中に、へルマン・ヘッセの「車輪の下」があって、これが彼とヘッセとの出会いのきっかけだった。その後、通学していた高校近くのT書店で、手にした「知と愛」。
ナルチスとゴルトムントという二人の友情を通して、思春期の希望と不安を繊細な筆致で描くヘッセにすっかり傾倒。
以降日本文学では掘辰雄、外国文学ではヘッセとなり、「春の嵐」「郷愁」「デミアン」「荒野の狼」など数冊のヘッセ著作が愛蔵書として本棚の一角を占めることになった。また、学生時代は、リルケやハイネなどの詩を手軽な文庫本で親しんでいる。
‘73年の7~8月にかけて、県ユースホステル協会のヨーロッパホステリングの一員として、彼は30日間でパリ・アムステルダム・ゲント・チューリッヒ・ローマなど主要都市を巡り、ドイツではケルン・ハ―ゲン・フランクフルト・ミュンヘンなどを訪ねている。
ノイシュバンシュタイン城で名高いロマンチック街道の一都市ローテンブルグでの印象記を次に記す。
― 数百年前そのままと思われる石畳の道々(略)中世そのままの風情を残すローテンブルグ。夕食後に城壁の外の谷あいにある散歩道で、そぞろ歩きを楽しんだ。―
そして、ミュンヘンでは、美術館の壁面を埋めるデューラーの油彩画に圧倒されている。
年末になると、毎年いろいろな所で「第九」の演奏が恒例化。作曲は言わずと知れたベートベン、その5番目の交響曲「運命」とともに広く知られている。三矢自身は、音がひしめき合う交響曲よりは、むしろピアノ協奏曲「月光」のような曲が好みだが・。「ローエングリーン」などの楽劇で有名なワグナーもドイツ生まれだ。
* * *
前回のイギリスのように、手がかりになる人名一覧が無いので、この文を綴るために、本棚のアチコチから抜き出した抜粋ノートや読書録。こういう形で利用するなど考えてもいなかったが、確認のため参照していると、その当時に、彼が過ごした時間や驚いたり共感したことの一部が脳裏に蘇り、古いアルバムをめくるかの印象が強かった。