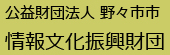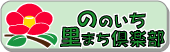「ああ、そういう小説作法の歴史的な発展があって・・」
と、彼は学生時代に読んだ本のいくつかを思い浮かべた。読書ノートをあらためると、「ジャンクリストフ」や「マリーアントヮネット」などに次いで63年の10月ころ、ドフトエフスキーの「カラマーゾフの兄弟」を読んでいる。
これらの作品は、世界文学全集本という体裁で活字がぎっしり組まれ、なおかつ、500ページ前後と分厚いので、上下巻を読み切るのに二週間くらい要していたようだ。
その頃は、小説の歴史的な変遷など全く意識になく、ただ、そのドラマ性や心理描写の深さに感動し、「今しか、こういう本は読めないだろう」と、むさぼるように読破していた。
* * *
昨年の二月下旬、湯川豊氏の講演“丸谷才一の残したもの”を聴く機会に恵まれた。僻村塾の主催だが、会場が千代女俳句館だったので、会場のロビーホールは満席の状況。
編集者として作家丸谷との付き合いや、その間にあったエピソードなどの紹介は、楽しめる内容だった。高名とは知っていたが、丸谷氏の著作は手元になかったので、帰りがけ並べられていた本のなかから三矢が手にした一冊が、「文学レッスン」だ。その中の一節が次の文。
― 18世紀のイギリスの長編小説が世に広まって、フランスに渡って、そこでディドロその他思想家たちの
知的な動向と結びついてまた発展した。それがロシアという辺境に及んだときに、19世紀ロシアの大小説という大変な騒ぎになった。―(注1)
軽妙な丸谷の文章に惹かれて読み進んでいると、この文節に出会った。その瞬間、彼の胸中に冒頭の納得と言うかひとつの感慨が浮かび、青年期へのワープとなった。多分、小説の読後にどうしてロシアでこれほど重厚な作品が生まれたのだろうか、という疑問を抱いていたのだろう。
* * *
社会人になっても、この延長線上で、「エヴェゲニィ・オネーギン」(プーシキン)、「アンナ・カレリーナ」(トルストイ)、「罪と罰」(ドフトエフスキー)など、ロシアものを読みついでいる。
―「おっちゃんは外国文学はどんなのを読みましたか」「昔の学生は、ロシアものに打ちこんだ。ツルゲーネフ、トルストイ、ドフトエフスキー、・(略)」―(注2)
この文章を書き綴ろうとしていた彼の後を押すように、暇つぶし的に手にした文庫本に、上記の文節があった。
文庫本の作家は、彼の一廻り上の年代。その人たちも、同じ空気の中で青年期を過ごして来たのだなという感慨である。
(’14-1-20)
[蛇足]:「スペクティター」(日刊紙)の連載小説は18世紀最大の文学的新機軸と言うべき長編小説(ノベル)を生む契機となった。(注3)
注1;丸谷才一著「文学レッスン」-44-
注2;田辺聖子著「女の居酒屋」-122-
注3;V・リヴジンスキー著、岩瀬孝雄訳「週末は楽しい」-107-
野々宮 三継 随筆集「林口川のほとりから」トップページはこちら
https://nono1.jp/modules/tinyd2/index.php?id=11