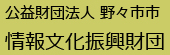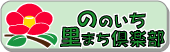「あゝ、ここでも触れていたんだな」
三矢は、若年時の読書での理解力というか、読みの浅さに改めて思い至っている。その本は78年5月1刷、巻末に同年6月29日読了と記しているから、出版間もない。彼の30代半ばの頃だ。
-長嘯隠士のいはく、客は半日の閑を得れば、あるじは半日の閑をうしなふと。素堂、このことばを常にあはれぶ。予もまた、
うき我を さびしがらせよ かんこ鳥
とは、ある寺に居て言ひし句なり。―(注1)
引用文は尾形仂著「芭蕉の世界」第五回『笈の小文』の旅の一節である。蕉風の句を味わうにあたって、同氏はさらに数ページ後に次のような文を綴っている。
―木下長嘯子という人はどういう人か。本名を木下勝俊といって、秀吉の北の方寧子の甥に当る。もと若狭小浜藩主だったが、関ヶ原の合戦後、初め京都東山、のちに西山の山荘に隠棲し、隠者としては「冬の日」に出てきた、石川丈山の先輩格に当る人物。芭蕉たちからは、近世隠士のモデルと仰がれ、その家集「挙白集」は芭蕉たち蕉門の愛読(歌)書の一つになっていた。-(注2)
三矢はこの1月、Dキーン著「日本文学散歩」の分冊を読んでいて、数ページのコピーを残している。それにも木下長嘯子に言及する章がある。
-長嘯子が幽斎に師事して何を学んだのかははっきりしないが、中世の伝統に従って、和歌に奥義を習ったことは疑いない。おそらく幽斎は、近世の和歌の源である『万葉集』も長嘯子に手ほどきしたのだろう。しかし長嘯子の歌は、幽斎が吹き込んだ正統的な伝統に忠実であるよりも、むしろ清新で、因襲に束縛されない闊達な歌風のために知られることになった。-(注3)
この文節あたりが、蕉門に愛読された由縁を語っているのだろう。けれど、長嘯子が三矢の関心を引いたきっかけは、まったく別のところ。それは久隅守景描く「夕顔棚」だ。振り返ると、彼の学生時代に遡り、数学の研究成果によって文化勲章を受章した岡潔氏との出会いに始まる。
むろん、一介の学生と高名な数学者、直接の面識などあるはずもない。そのころ購読していた(昭和40年5月)、朝日新聞に掲載された同氏の随筆「春の日冬の日」。その文で受けた鮮烈な印象から、後に出版された「岡潔集」全五冊の購入(昭和44年初版)へと続き、次文の「夕顔棚」とのつながりだ。
―好きな画家は大観と久隅守景、外国ならゴッホ、ラプラードなどである。(略)
守景の実物は見ていないが、ある画家から新聞に出ていた写真版の「夕顔棚」を見せられ好きになった。この絵には半裸の夫婦よりも、それを見ている作者の気持ちが描かれている。いいかえれば、日常茶飯事にあらわれている心の動きを描いている。私自身いつも情緒だけを取り出して、それを見ようとしているのだから、こんな絵が好きになるのだともいえる(後略)-(注4)
残してあった資料やそれに記されたメモによれば、三矢が守景を最初に意識したのは’90年10月、石川県立美術館にある屏風「四季耕作図」で受けた感銘が原点。その直後に、岡潔集第二巻を再読しこの文節に出会うのだ。さらには’95年1月に開催された特別展“屏風絵の美”での「四季耕作図」との再会。その展観での感想文を送付したところ「石川県美術館だより」114号に全文紹介のハプニングも。
これらに混じり、守景に関する新聞記事(95・1 96・2 96・5)のスクラップなども挟まれ、加賀藩と守景の深い縁なども知見として加えている。ただ、この時期は、単なる庶民とは思えぬ人物?何か曰くがある・? 不思議なモチーフの絵と思いながら、絵の持つ魅力に気持ちが傾いていた。
その後も、金沢出身の藤岡作太郎著「近世絵画史」で、
―探幽門下で四天王の一人、加州候に仕ふること凡そ六年。画くところ豪放奇抜、法格に拘わらず。伝えいふ、守景その師を凌しを以て、破門せられぬと。-(注5)
など断片的な知識は増している。
「夕顔棚」の夫妻が、歴史上名のある人物の故事を作画上の動機としたとすれば、長嘯子の来歴を知った今、守景描くチョンマゲ姿はその人では・・と解釈しても、あながち、的はずれでもないだろう。
守景についてもう少しチェックしようと三矢は、本棚から「万有百科事典・美術」を取り出した。久隅守景の項には「夕顔棚納涼図」が載っており、
-紙本淡彩、二曲一隻、国宝。当時の風流隠士、木下長嘯子の「夕顔のさけるのきばの下すずみ 男はててれ(襦袢)めはふたの(腰巻)して」という和歌に取材した軽妙洒脱な絵―(注6)
との、まさにドンピシャの解説文。
長い年月の間、長嘯子や守景に関する断片的な情報を少しづづ蓄えるなか、最後に残った孔を埋めるかの切片を手にした三矢の胸中。それは、こま切れの断片が少しづつつながり、元の絵が徐々に浮かび上がってくるジグソーパズルの完成にも似た印象だ。
以下、D・キーン氏から再度引用する。
-1598年の秀吉の死、その二年後豊臣・徳川の戦端が開かれた。長嘯子の父家定は、姫路城に封ぜられており、徳川方についた。が、長嘯子の場合は、選択は明らかにずっとむずかしかった。彼は、豊臣秀頼と徳川家康の双方から、それぞれ、自軍のために伏見城を守れという命令を受けていた。石田三成の攻撃に対して城を守っていた軍勢の中には、徳川家名代の忠臣鳥居元忠があり(略)討ち死にした。彼も三成の軍勢に対して城を死守すべきか、それとも豊臣家の多年の恩顧に報いるべきか。日本の武士の伝統に従えば、これは切腹して然るべき状況である。ところが長嘯子は、城を脱出して京都に引きこもってしまった。-(注7)
徳川・豊臣の覇権争いに、あちらを立てればこちらが立たず・どの道を選んでも、身内や部下を見捨てることになる。そうした苦衷を味わう立場から逃げ出し「武士としてあるまじき・」との批判をあびた身であってこそ、長閑で穏やかな夕涼み・。その時間の貴重さというか、下世話ともいえる絵の含意が納得できる。
(‘15・9・6作成)
参考文献
注1・注2: 尾形仂著「芭蕉の世界」
注3・注7; ドナルド・キーン著「日本文学散歩」
注4 ; 岡潔集第二巻 -160-
注5 ; 藤岡作太郎著「近世絵画史」-27-
注6 ; 万有百科大事典・美術 -180-